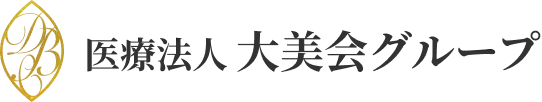Guideline
医療広告ガイドラインについて
- トップ
- >
- 医療広告ガイドラインについて
医療法人 大美会では、2018年6月1日に施行された「医療広告ガイドライン」に従い、厳正な社内チェックの基、医療広告ガイドラインに沿ったホームページ運用を行っております。
ガイドラインの目的
厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」で、患者様に客観的かつ正確な情報の伝達を行うことを目的としております。
※令和6年9月13日に最終改正された医療広告ガイドライン原文より一部抜粋
広告規制の趣旨
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあることから、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
禁止される広告の基本的な考え方
憲法第6条の5第1項の規定により、内容が虚偽にわたる広告は、患者等に著しく事実に相違する情報を与えること等により、適切な受診機会を喪失したり、不適切な医療を受けるおそれがあることから、罰則付きで禁じられている。 同様の観点から、法第6条の5第2項の規定及び医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。) 第1条の9により、次の広告は禁止されている。
- 比較優良広告
- 誇大広告
- 公序良俗に反する内容の広告
- 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者用を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告
治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。 また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。なお、医療広告に該当するか否かは、単に表現の直接性の有無だけでなく、情報全体の印象によって判断されるため、暗示的または間接的に医療広告と受け取られる可能性のある表現についても、同様に規制の対象となる。
医療広告は、直接的に表現しているものだけではなく、当該情報物を全体でみた場合に、暗示的や間接的に医療広告であると一般人が認識し得るものも含まれる。このため、例えば、次のようなものは、医療広告に該当するので、広告可能とされていない事項や虚偽・誇大広告等に該当する場合には、認められないものである。
名称又はキャッチフレーズにより表示するもの
【具体例】
- アンチエイジングクリニック又は(単に)アンチエイジング アンチエイジングは診療科名として認められておらず、また、公的医療保険の対象や医薬品医 療機器等法上の承認を得た医薬品等による診療の内容ではなく、広告としては認められない。
- 最高の医療の提供を約束。「最高」は最上級の比較表現であり、認められない。
写真、イラスト、絵文字によるもの
【具体例】
- 病院の建物の写真
当該病院の写真であれば、広告可能である (法第6条の5第3項第8号) が、他の病院の写真は認められない。 - 病人が回復して元気になる姿のイラスト
効果に関する事項は広告可能な事項ではなく、また、回復を保障すると誤認を与えるおそれがあり、誇大広告に該当するので、認められない。
新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載することによるもの
【具体例】
- 新聞が特集した治療法の記事を引用するもの
法第6条の5第3項第13号で認められた「治療の内容」の範囲であり、改善率等の広告が認められていない事項が含まれていない場合には、引用可能である。 - 雑誌や新聞で紹介された旨の記載
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、広告可能な事項ではないので、広告は認められない。 - 専門家の談話を引用するもの
専門家の談話は、その内容が保障されたものと著しい誤認を患者等に与えるおそれがあるものであり、広告可能な事項ではない。また、医薬品医療機器等法上の未承認医薬品を使用した治療の内容も、広告可能な事項ではなく、広告は認められない。
病院等のウェブサイトのURLやEメールアドレス等によるもの
【具体例】
- www.gannkieru.ne.jp
ガン消える (gannkieru) とあり、癌が治癒することを暗示している。治療の効果に関することは、広告可能な事項ではなく、また、治療を保障している誇大広告にも該当し得るものであり、認められない。 - nolhospi@xxx.or.jp
「nolhospi」の文字は、「No.1Hospital」を連想させ、日本一の病院である旨を暗示している。「日本一」等は、比較優良広告に該当するものであり、認められない。
広告の定義
次の (1) 及び (2) のいずれの要件も満たす場合に、法第2章第2節「医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告」の規定による規制の対象となる医療広告に該当するものと判断されたい。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること (特定性)
なお、(1) でいう「誘引性」は、広告に該当するか否かを判断する情報物の客体の利益を期待して誘引しているか否かにより判断することとし、例えば新聞記事は、特定の病院等を推薦している内容であったとしても、(1) でいう「誘引性」の要件を満たさないものとして取り扱うこと。ただし、当該病院等が自らのウェブサイト等に掲載する治療等の内容又は効果に関する体験談については広告に該当すること (その上で省令第1条の9第1号の規定に基づき禁止されること)。 また、(2) でいう「特定性」については、複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当するものであること。
医療広告として広告可能な範囲
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も広告をしてはならない。
監督機関およびお問い合わせ先
監督機関
厚生労働省 医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業
問い合わせ窓口
住所:大阪市中央区東心斎橋2-8-28周防町GEOビル3F
TEL:0120-373-889
詳しくは、医療広告ガイドライン(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。